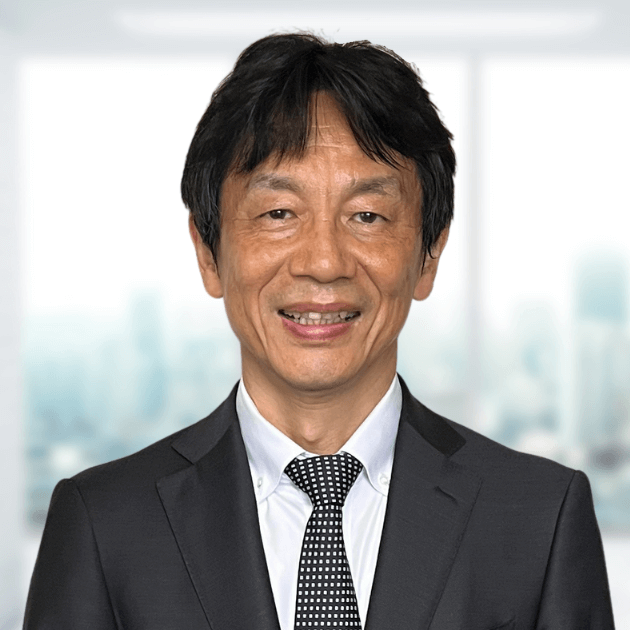
公認会計士・税理士
元銀行員、20年にわたり、創業融資、銀行融資、VCからの資金調達を支援てきました。資金調達の累計額は、100億円以上です。
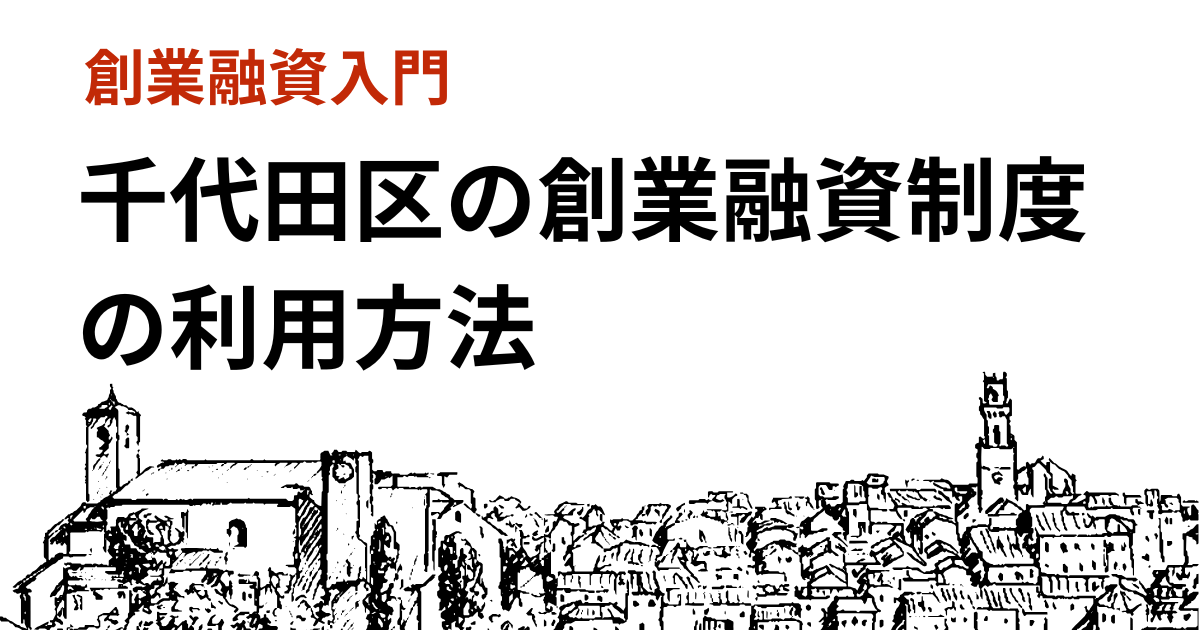
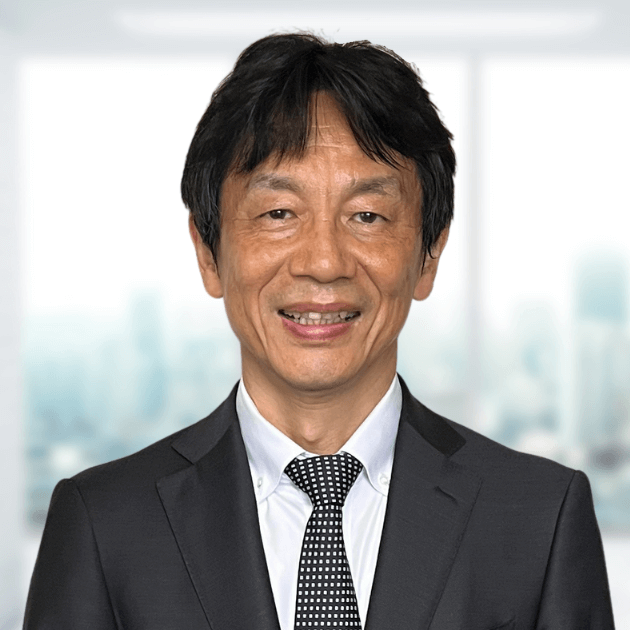
公認会計士・税理士
元銀行員、20年にわたり、創業融資、銀行融資、VCからの資金調達を支援てきました。資金調達の累計額は、100億円以上です。
千代田区の創業融資は、『商工融資あっせん制度』の中の融資制度の1つとして提供されています。
代田区の商工融資あっせん制度は、千代田区、東京信用保証協会、指定金融機関が協調して中小企業に融資する制度です。
区が指定金融機関に一定の資金を預託することにより、指定金融機関は、区の定める条件の範囲内で中小企業に融資をしてくれます。
必要に応じて、信用保証協会が保証を提供して融資を実現します。
さらに、区は利子の一部を負担してくれます。
千代田区の『商工融資あっせん制度』には、いくつかの制度がありますが、ほとんどは事業を1年以上営んでいることが条件となっています。
その中で、『創業資金』と言われる制度は、創業前、または事業期間が1年未満の中小企業を対象としています。
なお、千代田区で創業する方は、日本政策金融公庫の創業融資、東京都の創業融資も利用可能です。
| 代表者区分(借主です) | 区民 ※一般の場合は、やや条件が厳しくなります。下記注意書き参照のこと。一般とは、千代田区民以外のことです。 |
|---|---|
| 起業場所 | 千代田区に限ります。 |
| 資金使途 | 営業資金または設備資金(設備資金については見積書が必要です) |
| 融資限度額 | 2,500万円。 詳しくは、起業前の個人は2,000万円、起業後1年未満個人は2,500万円、法人の場合は、起業前から1年未満は1,500万円です。 |
| 名目利率 | 1.8% |
| 利子補給率 | 1.4% |
| 利子の本人負担率 | 0.4%。名目利率から利子補給率を控除した利率です。 |
| 融資期間 | 7年以内 |
| 据置期間 | 12ヶ月以内 |
| 返済方法 | 元金均等割賦返済 |
| 保証料補助 | 全額補助 |
| その他の条件 | 融資実行後6か月が経過した時点で、中小企業診断士による経営のフォローアップ診断を受ける必要があります。 |
※区民以外の一般の方の場合は、諸要件はやや厳しくなります。融資限度額が1,000万円となり、保証料補助は、東京都融資制度の要件を満たせば、東京都の信用保証料補助である3分の2補助が受けられる場合があります。ただし、町会加入企業等は、限度額が1,500万円となります。
法人の場合は、代表以外の連帯保証人は不要です。しかし法人の代表は、会社の連帯保証人となる必要があります。
個人の場合は、個人が責任をもつので、連帯保証人は不要です。
担保は原則不要です。
申込は予約制です。電話で予約のうえ、来庁する必要があります。初めての申込の場合、金融機関や会計事務所等が代理で申し込むことはできません。
担当部署は、下記の通りです。
地域振興部商工観光課経営相談・融資担当
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-4344(受付:平日9時~17時)
ファクス:03-3261-5908
まずは、中小企業診断士と数回、面談をすることになります。(所要時間は約40分。初回は午前9時~。その後は1時間単位で最終回は午後4時~)。面談を重ねながら、必要書類である創業計画書を作成します。
創業計画書の記入の仕方は、経営相談員が説明してくれます。
フォーマットは、『千代田区のホームページ』からダウンロードしてください。
千代田区は、すべての金融機関と協調している訳ではありません。
千代田区の起業資金を利用できる金融機関は、限定されています。
『千代田区のホームページ』で指定金融機関一覧を確認してください。
指定金融機関の銀行窓口では、申し込みできません。
メリットとしては、金利が0.4%と安いことと、信用保証料が全額補助されることです。日本政策金融公庫の創業融資の金利が2%前後なので、金利負担はかなりお得です。
デメリットは、いくつかあります。
第一に、無担保、無保証が原則ではないということです。会社の場合、多くの場合、経営者が保証人とならなければならないので倒産した場合に免責されません。
第二に、融資実行が遅い点です。区のあっせんを受けるためには、経営相談員の面談が数回必要とされていることと、多くの場合、金融機関と信用保証協会の両方の審査が必要となるためです。日本政策金融公庫の創業融資に比べて融資実行が約2ヶ月遅れます。そのため、区の創業融資だけに頼っていると創業時期がその分遅れて売上機会を喪失します。金利の安さを考慮しても、この遅れは問題です。ですので、日本政策金融公庫の創業融資のバックアップとして使うべきでしょう。
三つ目のデメリットは、融資実行後6カ月後に中小企業診断士のフォローアップ診断を受けなければならないことです。準備をしたり、診断を受けたりする時間を取られます。