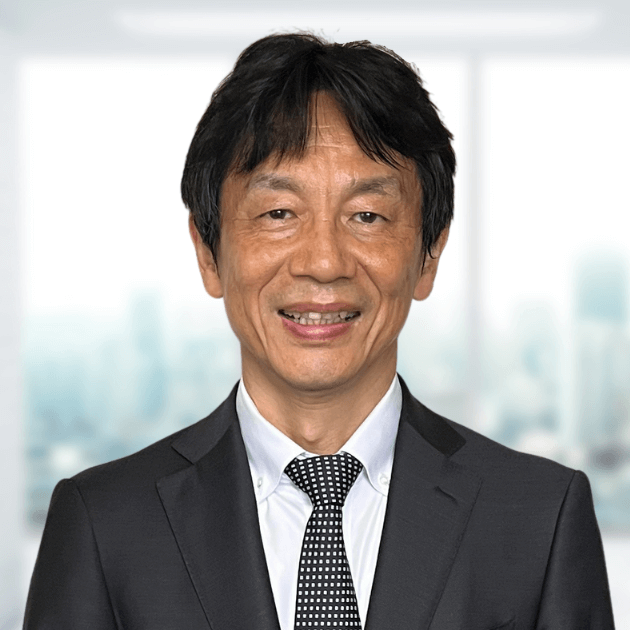
公認会計士・税理士
元銀行員、20年にわたり、創業融資、銀行融資、VCからの資金調達を支援てきました。資金調達の累計額は、100億円以上です。
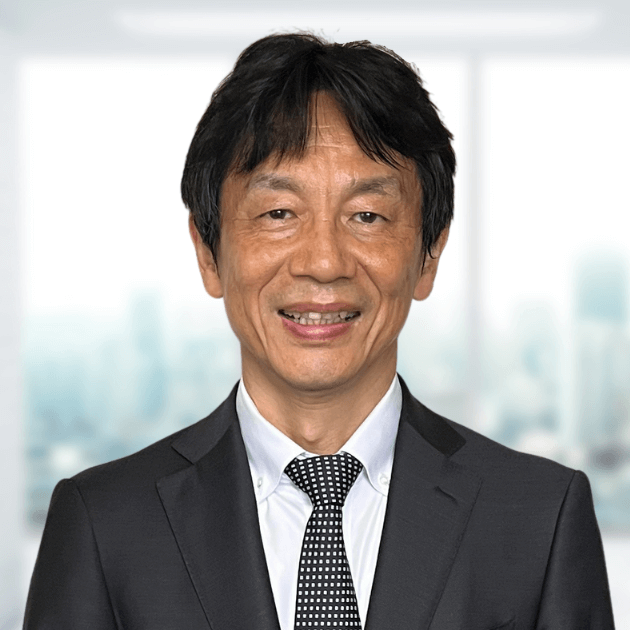
公認会計士・税理士
元銀行員、20年にわたり、創業融資、銀行融資、VCからの資金調達を支援てきました。資金調達の累計額は、100億円以上です。
個人事業主が創業融資を申し込む場合には、確定申告書の控えが必要となる場合があります。開業した翌年に、創業融資に申し込んだというような場合です。例を挙げれば、開業したのが、12月1日だが、創業融資に申し込んだのが、翌年の3月15日だというようなケースです。無担保、無保証、特別な低金利の創業融資は、税務申告が2期終了するまでは対象となるので、よく発生するケースです。ただ、開業した年と創業融資を申し込んだ年が同じ暦年であれば、不必要です。また、サラリーマンが個人事業を始めた場合は、会社で年末調整をしてもらっており、確定申告はしていないので、不要です。
確定申告書をいったん提出するともう終わったものだと思って、控えをいい加減に管理して、紛失してしまう人は少なくありません。ただ、紛失した場合は、創業融資を受けるためには必須資料なので、再発行してもらわなければなりません。
再発行するかどうかは、税務署の裁量事項ですが、結論からいえば、個人情報保護法により、時間はかかるものの、必ず再入手できます。
e-Taxの場合は、受信ボックスに受信通知と確定申告書控えのデータが残っているはずです。それらを、出力すれば、問題はありません。もともと、e-Taxの場合、確定申告書を送っても、受信通知しかもらっていません。受信通知で確定申告書の提出は、証明できます。ですので、受信通知を確定申告書のデータと一緒に、印刷すれば所得証明として十分なのです。
電子データの形で提出したいなら、電子申請等証明書制度を利用する方法もあります。これは、受信事実を電子的に証明してくれる電子データです。e-Taxから請求することができます。もらえるデータには電子署名がついているので、申告書の控えを、提出したことの証明となります。提出先が電子データを受け入れてくれるなら便利ですので、利用を検討してください。
紙で確定申告書を提出している場合には、情報開示手続きを利用すれば、確定申告書の控えを再発行してもらえます。手続きは、確定申告書を提出した税務署の窓口または郵送で行います。情報開示手続きは、個人情報保護法に基づく手続きですので、ほぼ100%間違いなく、再発行してもらえます。
具体的な手続きの流れは、次の通りです。
開示が不可の場合は、不服審査の請求ができます。税務署は、この請求をいやがりますので、書類上のミスがない限りは、開示は、認められます。
上記の開示手続には、約1か月前後の時間がかかります。創業融資の申し込みは、そのあととなるので、起業の全体スケジュールを考えて、余裕をもって再発行してください。
なお、e‐Taxを利用した開示請求等のオンライン申請の方法もあります。この方法では、e-Taxの「イメージデータで送信可能な手続」を利用して、職場や自宅のパソコンからオンラインによる申請が可能です。e-Taxの操作に慣れている方は、こちらの方法の方が早いのでお勧めです。
ほかに閲覧請求という手続きもあります。運転免許証等の本人確認書類と認印があれば、税務署で当日に閲覧できます。しかし、閲覧請求では提出した申告書を見ることができるだけで、書き写しはできますが、コピーをとったり、撮影したりはできないので、融資目的には役立ちません。さまざまな場面で必要となる書類ですので、時間はかかりますが、情報開示手続きで入手するのがお勧めです。
ほかに次のような場面で、確定申告書の控えが必要となります。
融資を受けるときは、多くの場合に、過去2年分の確定申告を求められます。
確定申告書の控えは、自動車ローンや住宅ローンでも必要となるので、見当たらないときは、早めに再発行しておきましょう。
e-Taxの申告書等情報取得サービスをつかえば、紙で申告書を提出している場合でも、提出書類の控えをPDFファイルで入手できます。過去3か年分の申告書控えを入手できます。このサービスをうけるには、電子署名のためにマイナンバーカードが必要です。この方法で入手した確定申告書控えは、金融機関が提出書類として認めてくれない可能性がありますので、当面は、e-Taxの受信データを使うか、情報開示手続きをとって